202303
гӮёгӮўгғјгӮ№ж•ҷиӮІж–°зӨҫ
еҮәзүҲзӨҫеҗҚгғЁгғҹпјҡгӮёгӮўгғјгӮ№гӮӯгғ§гӮҰгӮӨгӮҜгӮ·гғігӮ·гғЈ
еҢ…ж‘ӮгҒ®еӯҰзҙҡзөҢе–¶ : иӢҘжүӢж•ҷеё«гҒҜзҸҫе ҙгҒ§дё»дҪ“зҡ„гҒ«иӮІгҒЈгҒҰгҒ„гҒҸ
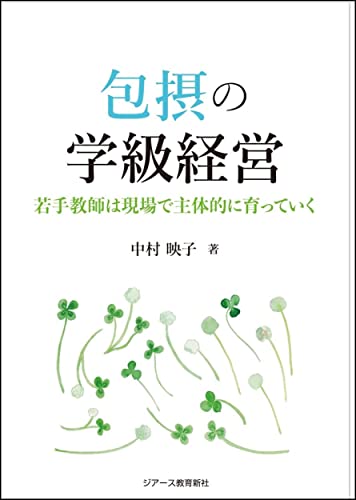
дёӯжқ‘,жҳ еӯҗ
пјҲ пјү
е®ҡдҫЎпјҡ2,860еҶҶпјҲ2,600еҶҶпјӢзЁҺпјү
еҲӨеһӢпјҡ
еҮәзүҲзӨҫгҒ®WebгӮөгӮӨгғҲгҒё launch
жӣёеә—еңЁеә«гӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜ
и‘—иҖ…з•Ҙжӯҙ
дёӯжқ‘, жҳ еӯҗпјҲгғҠгӮ«гғ гғ©, гӮЁгӮӨгӮігҖҖnakamura, eikoпјү
гӮҝгӮӨгғҲгғ«гғЁгғҹ
гӮ«гғҠпјҡгғӣгӮҰгӮ»гғ„ гғҺ гӮ¬гғғгӮӯгғҘгӮҰ гӮұгӮӨгӮЁгӮӨ : гғҜгӮ«гғҶ гӮӯгғ§гӮҰгӮ· гғҜ гӮІгғігғҗ гғҮ гӮ·гғҘгӮҝгӮӨгғҶгӮӯ гғӢ гӮҪгғҖгғғгғҶ гӮӨгӮҜ
гғӯгғјгғһеӯ—пјҡhousetsu no gakkyuu keiei : wakate kyoushi wa genba de shutaiteki ni sodatte iku